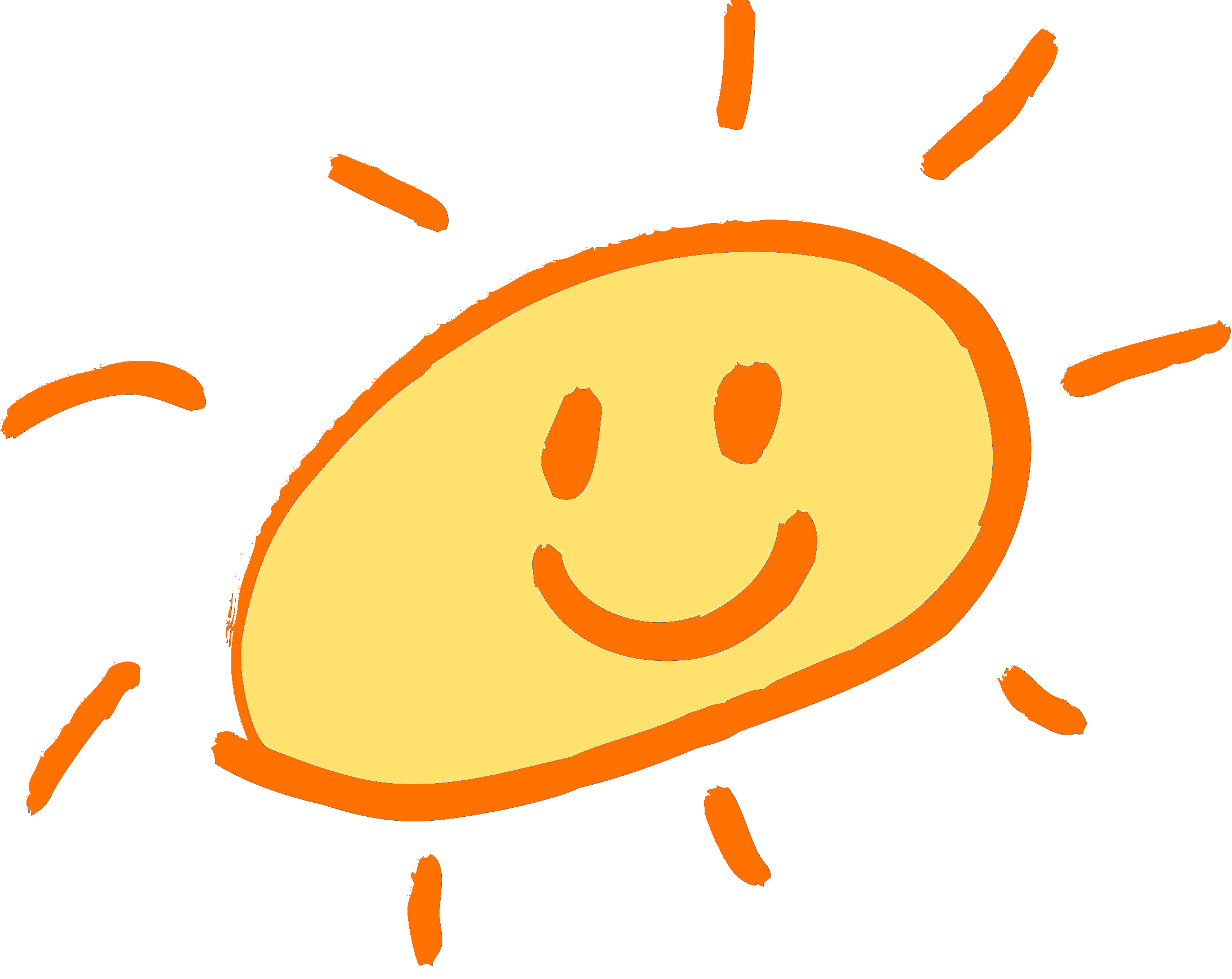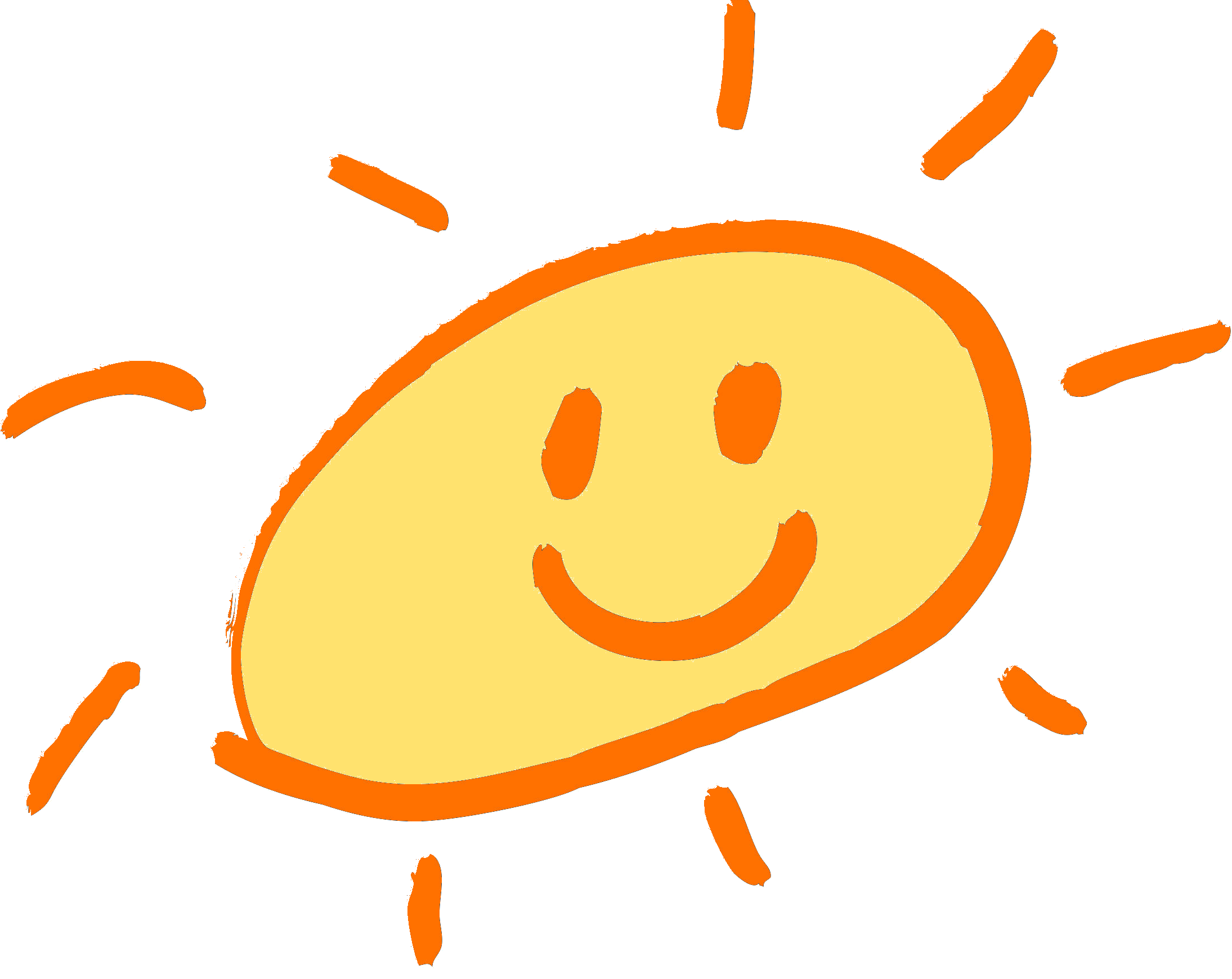「社会的養護」みんなで育てるということ by NPO法人 日向ぼっこ
今回のNTM特集は「社会的養護」―施設で子どもたちが育つということについて、考えてみようと思う。これは私たちにとって、古くて、新しい課題だ。子どもをめぐる問題でもあり、女性をめぐる問題でもある。家族の問題でもあり、社会の問題でもある。しかし、それは“子ども=問題”ではない。
社会的養護を受けて育った当事者たちが運営する団体がある。彼らが社会にでてからも集まれる場所、悩みや喜びをわかち合える場所を提供し、その声を外へ発信している。
子どもたちを養いまもるのは、施設の職員だけではない。タイガーマスクだけでもない。私たちみんなで育てよう―。社会的養護の本来の意味を、見つめ直してみる。
渡井隆行さん(34)が東京の児童擁護施設にやってきたのは10歳のとき。幼い彼は、最初そこを「少年院」だと思った。「自分は悪いことをしたからここに入っている。いいことをしていればいつかは出られる」―。18歳で施設を出るまで、ずっとそう思っていた。
父親の会社が倒産し、母親はひとりで彼を連れて上京した。夜働く若い母親は遊び盛りの息子の面倒をみられなくなっていく。学校にも行かず、家では食事もままならない。近所のコンビニからお弁当をもらって食べた。
施設に入っても小学生の間は母親のもとに帰りたい気持ちでいっぱいだった。
「外泊(施設から一時的に親元へもどること)すると母親のところから『帰りたくない!』って細いベッドの隙間に隠れたりしていた」
現在渡井さんは社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」の理事を勤める。本業はミュージシャン。男性ヴォーカルグループVOXRAYのメンバーだ。
「NPO法人『日向ぼっこ』は社会的養護を巣立った子どもたちが気軽に集える場所として誕生した。勉強会をやって当事者の声をあげていこうというところから始まって、当事者たちが気軽に集まれる場所をつくろうよ、となったのがきっかけ」
社会に出て、施設にも親元にも戻れずに孤立してしまう当事者は少なくないという。
「施設はいま生活している子どもたちが最重要だからアフターケアの対処がそこまでできていない。たまに施設内虐待とかもあるから帰りたくない子もいる」
施設で育つ子どもたちは我慢強い、と渡井さんは思う。
「よくも悪くも。言いたいことも閉じ込めてしまうタイプが多いんじゃないかな」
彼らは高校を卒業すると約27万円の支度金で自立しなければならない。高校へ進学しない子は15歳で施設を出る。彼らを渡井さんは「コトナ」と呼ぶ。
「オトナとコドモの間・・・日本の社会の大人は成人―はたち。でも社会的養護は18歳で大人。この19、20歳ってすごくきわどい」
厚生労働省によれば、社会的養護とは「保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対し、公的な責任として、社会的に養護を行う」ことを指す。
現在全国でその対象となっている児童は約4万7千人(「社会的養護の現状について」厚生労働省参考資料2013年3月)。そこに含まれるのは児童擁護施設に暮らす子どもたちだけではない。乳児院や自立援助ホーム、情緒障害児短期治療施設なども含まれる。里親のもとでより家庭に近い養育をうける子どもたちもいる。
一方で全国に589ヵ所ある児童擁護施設の5割が「大舎制」と呼ばれる1ユニットの定員数が20人以上の寮制。渡井さんが育った施設でも約60人の子どもたちが3つのユニットに分かれて生活していた。
東京都練馬区にある児童擁護施設「錦華学院」で現在の様子をみせていただいた。明治18年創立の歴史ある施設だ。1971年に新しくなった建物は修繕を繰り返し、2歳から19歳(社会に出てから一時的に戻ってきている人を含む)まで46人が生活している。すでに満員の状態だが、ときには児童相談所の一時保護施設が満員状態で、緊急一時保護として子どもを受け入れることもある。その背景にあるのは、子どもへの虐待だ。
「虐待を受けて入所する子が多い」と土田秀行院長。児童擁護施設は「衣食住だけではなく、心理的なケアが必要な、より治療的な施設になってきている」
厚生労働省の資料でも、虐待が養護の理由であるケースは、1987年からの約30年で3倍に増えている。児童擁護施設に入所する子どもの半数以上が虐待を受けており、その7割がネグレクト(育児放棄)だ(2008年)。
「僕は育児放棄という虐待の分類になる」と渡井さんは振り返る。しかし、誰かにはっきりと「悪いのはあなたじゃない」といってもらったのは社会にでてからだ。
「あなたが悪くなかったよってもっと早い段階で言ってくれていたら、もう少し気持ちは楽だったのかもしれないなと思う。だから僕は、生い立ちの整理は必ずしてくださいって施設の先生に言う」
なかには性的虐待や身体的虐待をうけて施設にくる子どももいる。「生い立ちの整理」というのは、子どもにとっては過酷すぎることもある。
「どこのタイミングで言うかは施設の職員さんの判断に任せないといけないが、ただゼロではないほうがいいなと思う。施設にいる間、守られている間に必ずしてほしいなというのが僕の願い。施設を出たら守ってくれる人がいなくなってしまう」
「日向ぼっこ」の理事として、渡井さんは社会的養護の当事者からさまざまな相談をうける。そのほとんどが親のことだ。
「お母さんに会いたいとか、お父さんに会いたいとか。お母さんにああいうことをされたのがすごくいやだったとか。なんだかんだいって、親だ」
渡井さん自身「もういいだろう」と思えるようになったのは最近だとか。それまでは静岡に住む母親を「ひとりの女性と自分」、「ちょっと関係ない人」としか見られなかった。変化がうまれたのは、彼自身が親になったからだ。
「うちは妻も当事者だからお互い親に頼れない状況。そうすると自分たちだけじゃどうにも無理だなって思う。お互いに仕事をしていたし保育園の時間も決まっているし。ああ、誰かに頼らなきゃいけないんだと。でも(自分たちの)親は頼れなかったんだなと思った。ヘルプを出せる人もいなかった」
2人目の子どもが生まれて「どうしても無理だ、助けてくれ」という息子のために、母親はふたたび東京へきた。
「負い目があるのかわからないが一生懸命やってくれた。だから当時者も頼らなきゃいけないんだなと。我慢しないで、無理なら無理って言えばいいんだと思う」
いま、渡井さんは子どもへのサポートと同時に親へのサポートを訴えている。「親を孤立させることは子どもを孤立させるのと一緒」だと思うからだ。
「みんなで子どもを養って育てていく、まもっていくというのが社会的養護。僕はそこに子どもだけじゃなくて親も含む。根っこをちゃんとやるべきだ」