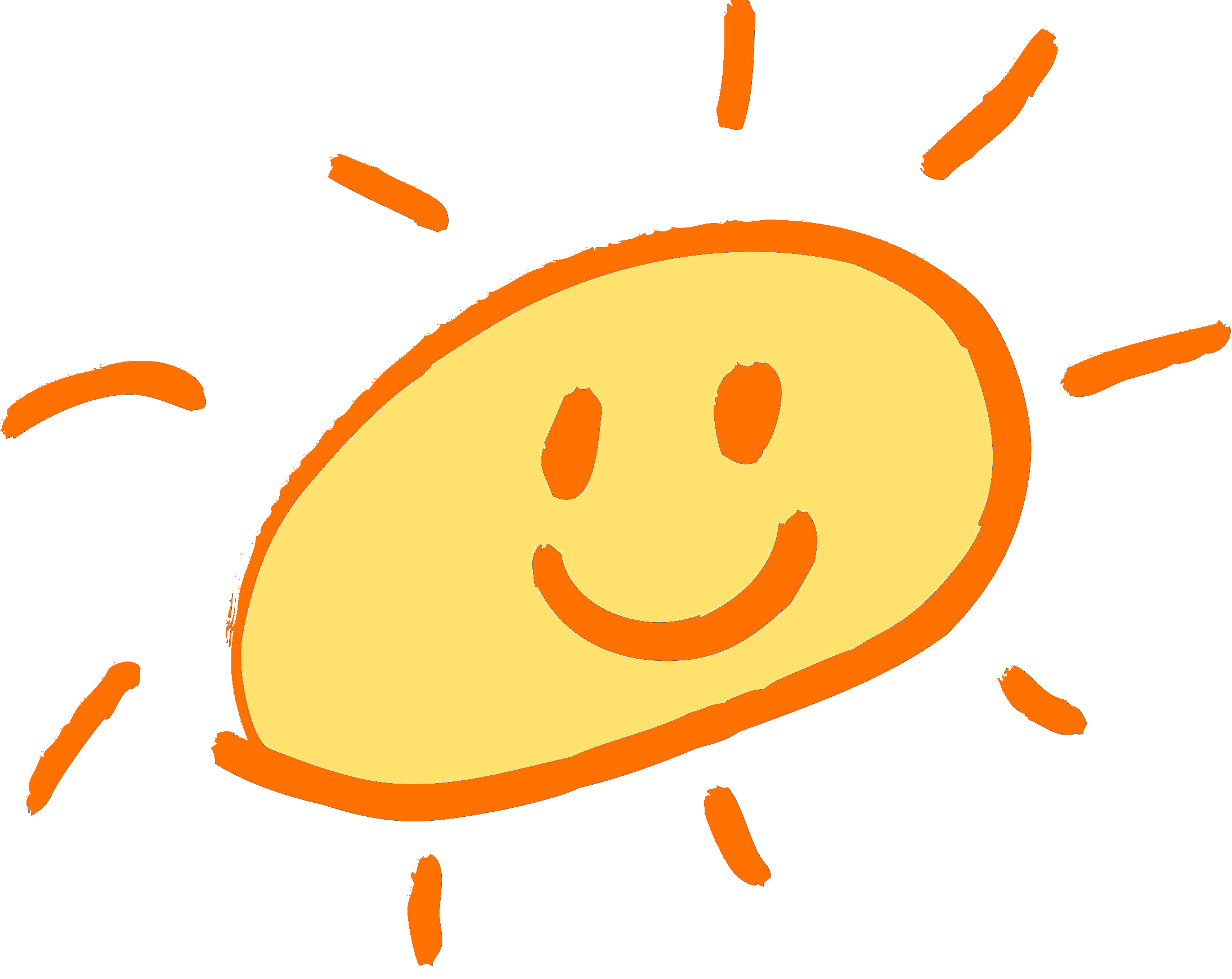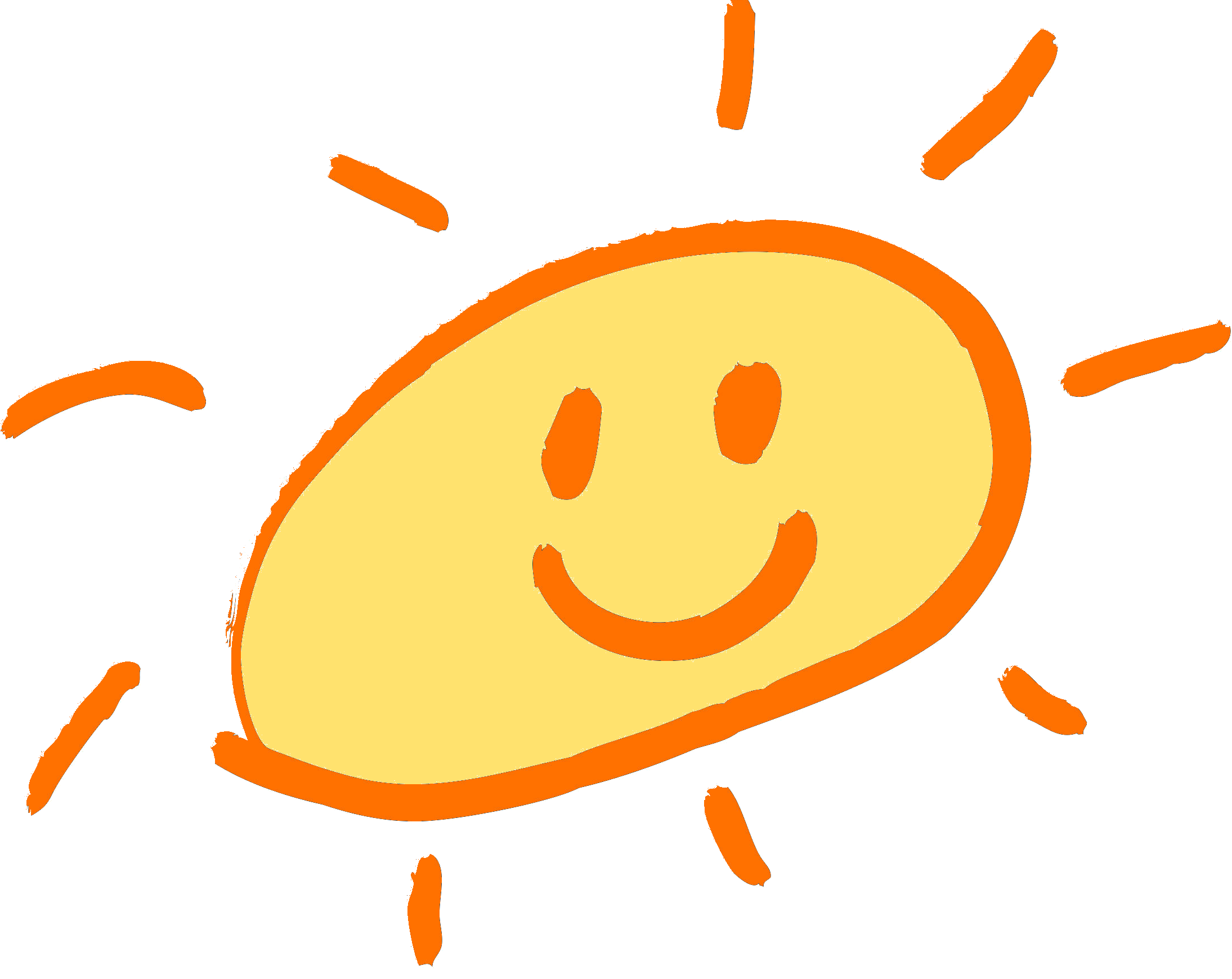NPO法人日向ぼっこは「多様性が尊重される社会の実現」を目指し活動する団体です。来館される方が安心・安全に集え、自由に過ごせる場所「日向ぼっこサロン」の運営をする「居場所事業」と、様々な方からお話頂いた事柄について、寄り添いながら一緒に考える「相談事業」、日向ぼっこに関わってくださる方々の声を集め、社会に向けて発信する「発信事業」を行っています。
 居場所事業 |
日向ぼっこに来館したいと思った方々が、安心・安全に集え、自由に過ごすことができ、様々な団体や人と繋がりを作れる場所として、「日向ぼっこサロン」を運営しています。お菓子を食べたりしながら、日々の生活のことや、自分自身が感じていることなどを話したり、読書や楽器演奏など、来館された方が自由に過ごせる場所を作っています。サロンの中で、勉強会を始め、来館された方々と一緒に考えながら様々なイベントも行っています。イベントの詳細は日向ぼっこカレンダーやFacebook、Twitter、Instagram、TIE UP PROMOTIONなどをご覧いただき、ご興味がございましたら、お気軽にご連絡下さい。 |
|---|---|
 相談事業 |
来館された時や電話、メール、お手紙などでお話頂いた色々な事柄について、寄り添いながら一緒に考えさせて頂いております(予約制)。お話された内容によっては、他機関とも連携しながら、様々な形でサポートが出来るようにしています。ご相談に応じて、食料や物品を送らさせて頂いています。また、日向ぼっこ基金を設け、貸付事業も行っています。 |
 発信事業 |
日向ぼっこの活動や、日向ぼっこに関わって下さる方々の声を集め、多くの方々にその声をお伝えするために、年一回「日向ぼっこ展覧会」を開催、書籍等の出版物や講演会やメディア、ウェブ等で発信しています。 |
※日向ぼっこの最新情報をご希望の方はメルマガ登録をお願いします。
日向ぼっこの変遷
| 2006年3月 | 「社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ」発足。社会的養護の当事者主体の勉強会を重ねる。 |
| 2006年〜2020年 | 特定非営利活動法人 児童虐待防止全国ネットワーク「子どもの虐待死を悼み命を讃える市民集会」運営委員就任。 |
| 2007年4月 | 青少年福祉センター様のご厚意により、東京都新宿区中落合に事務所としての場所を無償でご提供いただき、社会的養護のもとで生活した人たちが気軽に集える「日向ぼっこサロン」を開始。同時に、団体名を「社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ」に変更。 |
| 2008年7月 | 特定非営利活動法人格取得。 |
| 2008年8月 | 東京都より地域生活支援事業(愛称:ふらっとホーム事業。現:退所児童等アフターケア事業)を受託。 |
| 2009年4月 | (株)明石書店様のご厚意により、東京都文京区湯島にあるビルの1室を格安で借りられるようになったため、事務所を移転。 |
| 2009年6月 | (株)明石書店様より、『施設で育った子どもたちの居場所「日向ぼっこ」と社会的養護』を出版。 |
| 2010年4月~2018年 | 厚生労働省「社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究会」委員就任。 |
| 2011年2月 | 厚生労働省「児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会」委員就任。「社会的養護の課題と将来像」のとりまとめに携わる。 |
| 2011年9月 | 厚生労働省「児童養護施設運営指針ワーキンググループ」委員就任。児童養護施設運営指針・児童養護施設第三者評価ガイドラインの作成に携わる。 |
| 2011年12月 | 厚生労働省「社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会」委員就任。 |
| 2013年4月 | 前理事長の退職に伴い、理事長制を廃止するとともに、社会的養護の当事者団体としてではなく、活動することとし、活動の目的を「多様性が尊重される社会の実現」に変更。 活動の目的変更の3つの主な理由 1)社会的養護の当事者の方と同じような困難をお持ちの、社会的養護の当事者以外の人からの相談が来るようになった 2)当事者だから当事者の気持ちがすべてわかるわけでもない 3)社会的養護の当事者性の問題 ①社会的養護の当事者になるのは、多くの場合当事者の意思ではなく、偶然の発見や通報によることの方が多い。 ②現在、児童相談所から児童養護施設等への措置に至らず、家庭に返された人は社会的養護の当事者でないということになっている。 |
| 2015年7月 | 内閣府「子供の貧困対策支援情報ポータルサイトに関するヒアリング」に参加。 |
| 2017年8月 | 首都圏若者サポートネットワーク「若者おうえん基金」運営委員就任。 |
| 2018年8月 | 厚生労働省「先駆的ケア策定・検証調査事業(施設入所が長期化に至るケースの調査研究)検討委員会」委員就任。 |
| 2020年9月 | 新宿区下落合に事務所を移転。 |
| 2006年3月 |
|---|
| 「社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ」発足。社会的養護の当事者主体の勉強会を重ねる。 |
| 2006年〜2020年 |
| 特定非営利活動法人 児童虐待防止全国ネットワーク「子どもの虐待死を悼み命を讃える市民集会」運営委員就任。 |
| 2007年4月 |
| 青少年福祉センター様のご厚意により、東京都新宿区中落合に事務所としての場所を無償でご提供いただき、社会的養護のもとで生活した人たちが気軽に集える「日向ぼっこサロン」を開始。同時に、団体名を「社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ」に変更。 |
| 2008年7月 |
| 特定非営利活動法人格取得。 |
| 2008年8月 |
| 東京都より地域生活支援事業(愛称:ふらっとホーム事業。現:退所児童等アフターケア事業)を受託。 |
| 2009年4月 |
| (株)明石書店様のご厚意により、東京都文京区湯島にあるビルの1室を格安で借りられるようになったため、事務所を移転。 |
| 2009年6月 |
| (株)明石書店様より、『施設で育った子どもたちの居場所「日向ぼっこ」と社会的養護』を出版。 |
| 2010年4月~2018年 |
| 厚生労働省「社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究会」委員就任。 |
| 2011年2月 |
| 厚生労働省「児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会」委員就任。「社会的養護の課題と将来像」のとりまとめに携わる。 |
| 2011年9月 |
| 厚生労働省「児童養護施設運営指針ワーキンググループ」委員就任。児童養護施設運営指針・児童養護施設第三者評価ガイドラインの作成に携わる。 |
| 2011年12月 |
| 厚生労働省「社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会」委員就任。 |
| 2013年4月 |
| 前理事長の退職に伴い、理事長制を廃止するとともに、社会的養護の当事者団体としてではなく、活動することとし、活動の目的を「多様性が尊重される社会の実現」に変更。 活動の目的変更の3つの主な理由 1)社会的養護の当事者の方と同じような困難をお持ちの、社会的養護の当事者以外の人からの相談が来るようになった 2)当事者だから当事者の気持ちがすべてわかるわけでもない 3)社会的養護の当事者性の問題 ①社会的養護の当事者になるのは、多くの場合当事者の意思ではなく、偶然の発見や通報によることの方が多い。 ②現在、児童相談所から児童養護施設等への措置に至らず、家庭に返された人は社会的養護の当事者でないということになっている。 |
| 2015年7月 |
| 内閣府「子供の貧困対策支援情報ポータルサイトに関するヒアリング」に参加。 |
| 2017年8月 |
| 首都圏若者サポートネットワーク「若者おうえん基金」運営委員就任。 |
| 2018年8月 |
| 厚生労働省「先駆的ケア策定・検証調査事業(施設入所が長期化に至るケースの調査研究)検討委員会」委員就任。 |
| 2020年9月 |
| 新宿区下落合に事務所を移転。 |